
▲旧西国街道
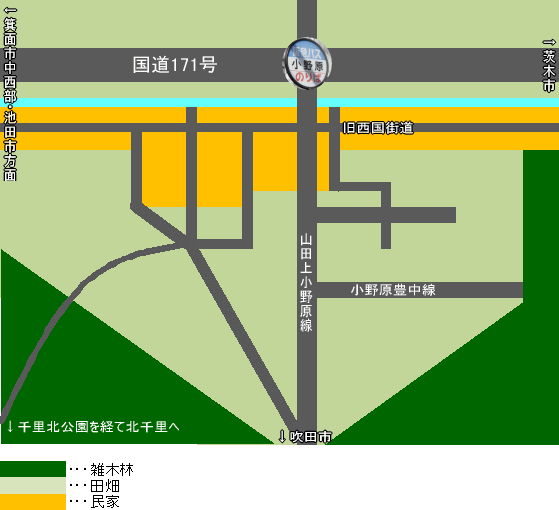

◎おのはらの沿革
| 南は吹田市、東は茨木市に接する、箕面市南東部の小野原(おのはら)地区。これらの市境部分には、今でも雑木林が残っているが、かつては小野原地区の広範囲を雑木林が占めていたらしい。それ以外の場所も田畑が多く、民家の大部分は、「旧西国街道」沿いに軒を並べていた。 | |
 ▲旧西国街道 |
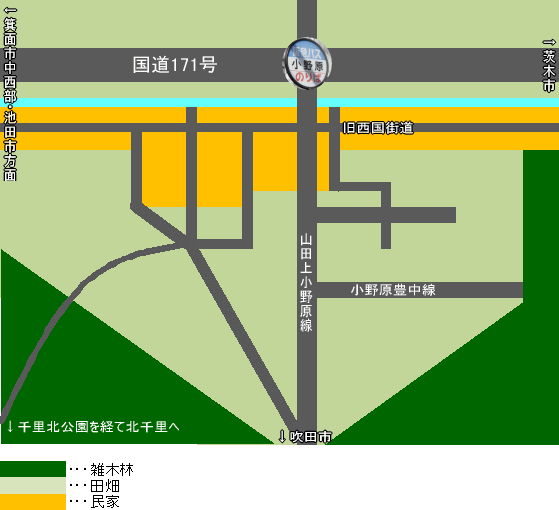 |
| 千里ニュータウン造成や万国博覧会が開催されて以降の1970年代に入った頃、その北に続く小野原(おのはら)地区に宅地開発が広がっていったのだ。 |
|
 |
|
| まずは、山田上小野原線(府道120号)を境として東側の「小野原東」地区に於いて、大規模な区画整理が進められた。マンションや高級一戸建て住宅が建設され、住民人口の流入が顕著となった。 たとえば、域内の豊川南小学校(私の母校)が1979年に開校した当初、児童数241人(9クラス)だったのが、5年後(1984年)には約2倍の509人(15クラス)に、10年後(1989年)には約3倍の738人(21クラス)にと、着実に児童数が増えていった。 かつては国道171号沿いにバス路線(阪急石橋〜JR茨木/千里中央・北千里〜粟生団地など)が走っていただけで、「小野原」バス停まで北上するしかなかったこの地区だが、1990年6月には、新しいバス路線「小野原東線」が運行開始となった。域内のスーパーマーケットなどが整備されたこともあり、住環境としては非常に住みよい住宅街となった。
|
| 山田上小野原線(府道120号)を境として西側の「小野原西」地区も、小野原東地区が発展途上だった頃から、区画整理・宅地開発の計画が進んでいた。実際、私が小学生時代の話だが、あたかも2〜3年後には一戸建て住宅が立ち並ぶかのような、道路や住居用敷地の区画が整っているエリアが見られた。しかしながら、一向に家が建つ気配がなく、小野原東地区の発展ぶりとは正反対の静けさが見られた。当時まだ小学生だった私には、「なぜだろう?」と疑問を持つ日々だったのだが、後から考える限り、バブル崩壊の影響に他ならない。 区画整理着工済みエリア以外にも、市販の地図に点線で記された道路計画があることは知っていた。たとえば、上記地図上にも記した「小野原豊中線」。小野原と豊中市(はるか南西方向)を結ぶ道路として計画されているのに、小野原西地区などは長らく未着工(部分開通のみ)のままだった。早く開通してくれれば便利なのになぁと思いながらも、全く着工される気配はなく、最近まで雑木林や田畑が残っていた。 そんな中、少しずつ発展が見られたのは・・・ 1991年:「千里国際学園」開校。 1993年:新しいバス路線「小野原住宅線」運行開始。 私が高校生だった頃で、自己紹介の時は「北千里にほど近い、小野原というところに住んでいます。千里ニュータウンの北の外れで、いま最も発展中のエリアです。」などと誇らしげに話したものだった。 |
  |
| 小野原西地区の区画整理事業が本格的に始まったのは、2000年頃。私が大学生になり、小野原(おのはら)を離れて信州で暮らすようになってからの話だ。 |
||||||
| まず、同じ小野原西地区でも、国道171号近辺が整備され、各種商業施設が充実した。併せて、従来からあったバス停の「小野原」〜「新家」(約850m西方)の間に、「小野原西」バス停が新設された。これにより、石橋方面へ行く時は「新家」バス停を、茨木方面へ行く時は「小野原」バス停をという風に使い分けざるを得なかったのが、バス停間距離の短縮により便利になったのだ。 |
|
|||||
| そして、長らく雑木林や田畑だったエリアも、大規模な造成工事が始まっている。幼少期の頃に見た自然の景色が、かつての面影を留めないほど変遷しているのには、何気に寂しいものがある。が、今後流入してくる人々には、ぜひ小野原(おのはら)という住みよい住環境を満喫してほしいと、今や住民ではない私が願っていたりする。 | ||||||
 |
 |
| ▲造成工事中の小野原西地区 | ▲同じく、造成工事中の小野原西地区 |
●新たな最寄駅「豊川」
小野原(おのはら)を東に出てまもない所(茨木市域)にできたのが、モノレール彩都線「豊川」駅。モノレールは、都心へは直接アクセスできないが、行く場所によっては便利に利用できる新路線である。
 |
 |
| ▲豊川駅から北に延びるモノレール彩都線 | ▲国道171号をオーバークロスするモノレール彩都線 |